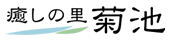<簡体字>
安国寺
安国寺见证了菊池家族史上的不少艰难时期。这座寺庙由足利幕府(1336-1573)的第一代将军足利尊氏(1305-1358)下令创建。1336年,在朝廷和武士统治支持者的对峙中,足利尊氏成为最后的胜利者,站在朝廷一边的菊池家族最终被足利尊氏的军队击溃。
1339年,随着统治趋于稳定,足利尊氏下令在所有地区建造安国寺,藉此安抚战败方、告慰在镰仓幕府(1185-1333)倒台引发的战乱中遇难的亡灵。在菊池家族治下的肥后国(今熊本县;“国”是日本古代行政区划,有别于“国家”),既存的寿胜寺被选中并更名为安国寺。
百余年后,安国寺再次目睹了菊池家族的另一出悲剧。家主菊池政隆(1491-1509)被家臣们废黜后试图反攻,但以失败告终,最后退至安国寺,在寺院被对手付之一炬前自尽。
1515年,安国寺重建,当时建造的本堂(正殿)是现在寺内唯一的建筑。菊池政隆的陵墓则在本堂后面稍远处的山脚下。
※关于菊池氏(菊池一族とは)
※其他文化财产信息板也有多种语言版本。(他の文化財説明板も多言語化しています。)
<繁体字>
安國寺
安國寺與菊池家一同度過了歷史上許多艱困的時期。這座寺廟是足利幕府(1336-1573)第一代將軍足利尊氏(1305-1358)下令創建的。1336年,在天皇與武士階級之間的權力爭鬥中,足利尊氏取得了勝利,與天皇同一陣線的菊池家慘敗於足利尊氏的軍隊。
1339年,足利尊氏的統治趨向穩固,他下令在每個地區建造安國寺,用以安撫戰敗對手、慰藉在鐮倉幕府(1185-1333)滅亡後的戰亂中罹難的亡靈。在菊池家管轄的肥後國(今熊本縣;「國」是日本古代行政區劃分,有別於「國家」),既存的壽勝寺被選中並更名為安國寺。
百餘年後,安國寺再次目睹菊池家另一場悲劇。當時的家主菊池政隆(1491-1509)被家臣們廢黜後試圖奪回政權,但以失敗告終。最後他退至安國寺,在對手焚毀寺廟之前自絕身亡。
安國寺重建於1515年,當時建造的本堂(正殿)是目前寺內唯一的建築。菊池政隆的陵墓位於本堂後方稍遠處的山腳下。
※關於菊池氏(菊池一族とは)
※其他文化財產資訊板也有多種語言版本。(他の文化財説明板も多言語化しています。)
安国寺(安国寺の堂宇)
延元4年(1339)、室町幕府の将軍足利尊氏は、後醍醐天皇及び元弘の変以降の戦没者の追善、また国土安穏の祈祷を目的として全国に一国一寺の安国寺令を下しました。肥後では青原山寿勝寺が選ばれ、寿勝安国寺と改称し、これを機に伽藍は旧地堂床から現在地に移されました。
永正6年(1509)、菊池23代政隆と武経(阿蘇惟長)が久米原で戦火を交え、敗れた政隆は安国寺に入り自刃して果てました。この兵火で伽藍は焼失し、6年後の永正12年(1515)に再建されたのが現在の堂宇です。
堂宇は南向きで、元の部分を礎石から推定すると、横幅が約5m、奥行きが約6mで、それに玄関が付きます。明治20年(1887)に増築が行われ、奥に約3mを継ぎ足して仏間とし、外回りに約1mの手摺り付き濡れ縁を拡張してあります。