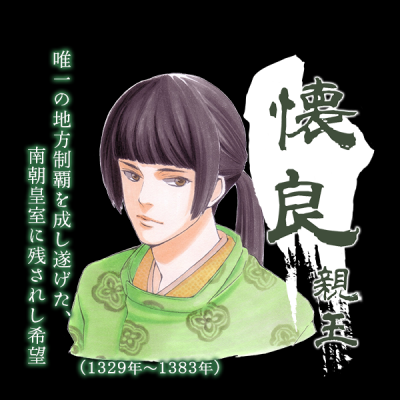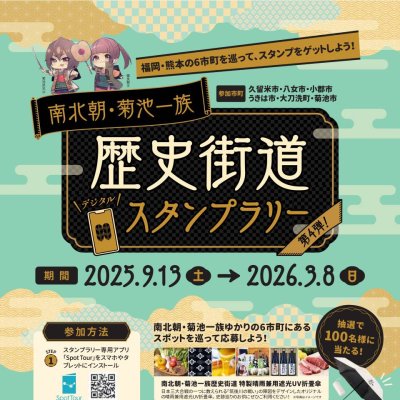もう一人、菊池の文教に大きな功績を残した人物、それが為邦の長男21代重朝です。
もう一人、菊池の文教に大きな功績を残した人物、それが為邦の長男21代重朝です。
一族は、儒学の中でも大義名分を重んじ主従の道を強く唱える朱子学を深く学び、菊池氏の行動の規範となしました。重朝は為邦や隈部忠直(くまべたたのぶ)と相談し、1472(文明4)年に孔子堂を建て文教を奨励しました。忠直は、学問に優れたと評判の重臣です。
1476(文明8)年、一人の高名な僧が菊池にやってきました。京都南禅寺の桂庵禅師(けいあんぜんじ)が九州行脚の途中、菊池で学問が盛んであるとの評判を聞きつけて立ち寄られたのです。禅師は、当時日本一の学者と称されてしました。思いもよらない高僧の来訪に重朝は大喜び、もろ手を挙げての大歓迎。忠直ともども、早速、その教えを請いました。さらに翌年、孔子の祭りである「釈奠の礼(せきてんのれい)」を催行します。禅師は、重朝・忠直の好学を喜び、徳の高さを称えました。
二人が作った詩は遠く京都まで伝わり、人々の賞賛の的となり、僧たちの間でこぞって詠われたといいます。「肥の国たるや、文あり武あり、民は礼節を知る、実に邦臣の仁化の及ぶ所なり」京都五山の僧は、このように感嘆の声をあげました。
それから5年の月日を経た1481(文明13)年、重朝の館をはじめ主だった家臣や僧の館から、朗々と歌を詠む声が流れていました。「菊池万句(まんく)」と呼ばれる大連歌の会が開かれているのです。20か所の会場それぞれに「月」をテーマに500句ずつ、なんと一日のうちに1万句を詠むという、驚くべき催しでした。この会の成功は、菊池の人々の詩趣や教養の高さを世に広く知らしめることとなりました。
菊池氏代々、連綿と続いてきた好学の精神は次第に大きな流れとなり、この時期に確かな実を結んだのです。