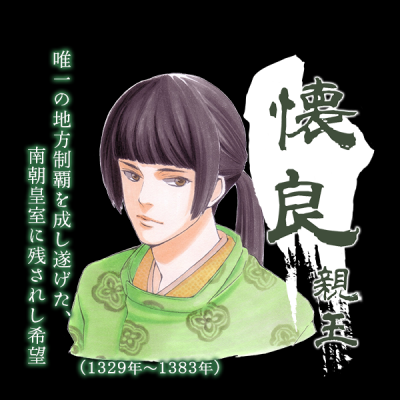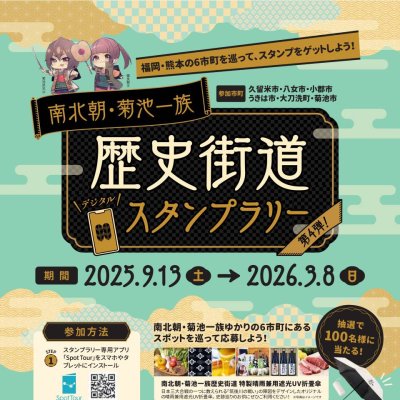御松囃子御能(おんまつばやしおのう)は、7歳で奈良の吉野を出発し、12年もの歳月をかけて菊池に入城した懐良親王のために、武光が催させたのが始まりとされています。
征西将軍として九州を平定するという父の命を受けて出立し、長く厳しい旅路の果てに菊池にたどり着いた懐良親王。一方武光は、実力で当主の座についた後、南朝方として一族の更なる台頭を目指していました。征西将軍の存在は戦の大義名分そのものであり、菊池一族の武力と合わせることで、九州制覇を現実のものにしようと目論んでいたのです。
 二人は互いになくてはならない存在であり、親王の菊池への入城はそれぞれに万感の想いだったことでしょう。武光はそんな親王へのもてなしとして、能を上演します。遠い故郷から遥かな時間と距離を経て、辺境とも呼べる地にやって来た親王にとって、その雅な芸事は、幼少の頃に過ごした都を偲ばせるものだったことでしょう。
二人は互いになくてはならない存在であり、親王の菊池への入城はそれぞれに万感の想いだったことでしょう。武光はそんな親王へのもてなしとして、能を上演します。遠い故郷から遥かな時間と距離を経て、辺境とも呼べる地にやって来た親王にとって、その雅な芸事は、幼少の頃に過ごした都を偲ばせるものだったことでしょう。
「京を発って12年……この地で、このように雅なものを見られるとは……。都で過ごした日々を思い出すのう」
二度と帰郷は叶わないことを覚悟したであろう親王が、その心遣いにどれほど慰められたか、想像に難くありません。
現在、御松囃子御能は『菊池の松囃子』として国の重要無形民俗文化財に指定されています。松囃子とは、中世に流行した芸能で、元々は新春を祝う年頭の祝儀として行われていました。菊池の松囃子は、天下泰平、国家安穏などを願った舞で、現在は菊池神社の秋の例大祭として、毎年10月13日に行われています。
素朴な舞の振りや瑶(うたい)の調子は、現存している松囃子の中でも古風なもので、少なくとも室町時代から継承されているものと考えられています。菊池の人々は、菊池一族が亡びた後もその遺徳を敬い、この舞を欠かすことなく忠実に守り伝えてきました。人々の一途な想いが、今日の私たちに、親王が観覧したであろうそのままの舞を見せてくれるのです。
Next→05針摺原の戦い(サイト内リンク)