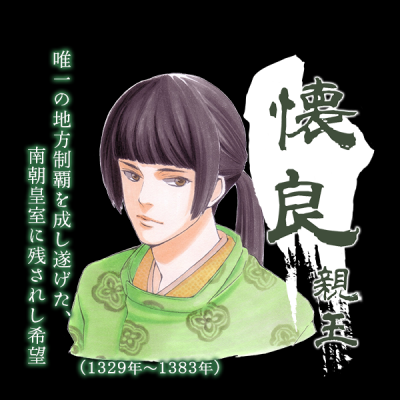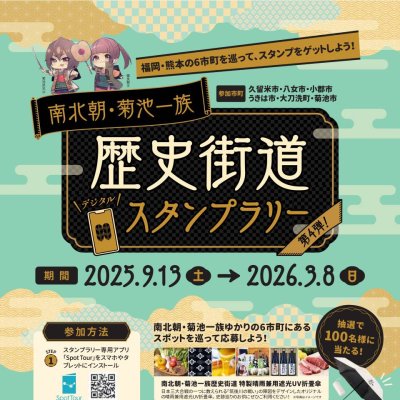筑後川の戦い
1352年、中央における北朝方の内紛に決着がつくと、九州の三すくみ状態も解消されました。菊池への服従を誓ったはずの少弐頼尚(しょうによりひさ)は、その舌の根も乾かぬうちに武光に対抗し、いよいよ1359(正平14)年、両者は現在の福岡県小郡(おごおり)市で激突することになります。「筑後川の戦い」(大保原合戦/おおほばるかっせん)と呼ばれるこの戦は、日本三大合戦の一つに数えられるほど大規模なもので、南朝方4万騎に対して、北朝方は6万騎と言われる大軍勢で筑後川の対岸に立ちはだかりました。
数の不利を覆すために、武光は一計を案じます。以前、針摺原(はりすりばる)の戦いで頼尚を救援した際に渡された、「子孫七代に至るまで決して菊池に弓を引くべからず」と記された血判状を旗の先にくくりつけ、両軍からよく見えるように行進して見せたのです。戦うための大義名分が何よりも大切だったこの時代、大将の不徳な行いを見せつけられた北朝軍は大いに士気を下げることになったでしょう。
結果、南朝軍はこの戦いに勝利し、その後九州の北朝勢を一掃して九州制覇を成し遂げます。筑後川の戦いの痕跡は、「大刀洗」「宮の陣」など、現在もこの地方の地名の中にも見ることができます。
征西府の絶頂期
少弐氏の追討後、征西府は菊池から大宰府に移されました。当時、大宰府は九州の中心地であり、かつて官位にあって大いに繁栄していた時代の象徴的な場所であったため、この場所を押さえることは一族にとっての悲願とも言えました。これから12年間にわたり、菊池一族の黄金時代を築くことになるのです。
この時代、大宰府の征西府がいかに繁栄していたかを物語る逸話が残っています。日本人の海賊である倭寇(わこう)に頭を悩ませた明(みん)国が、室町幕府でも北朝朝廷でもなく、懐良親王に取締りを命じる使者を出したのです。初めは使者の横柄な態度に激怒していた懐良親王でしたが、「明の後ろ盾」という魅力に着目します。そして明と正式に約束を交わし、室町幕府に先んじて、朝貢貿易を行う「日本国王良懐」として認められたのです。後に3代将軍義満が日明貿易を持ちかけた時、明国から「良懐の『家臣』とは貿易できない」と断られ、しばらくは懐良親王の代理という立場を取らざるを得なかったという話も伝わっています。