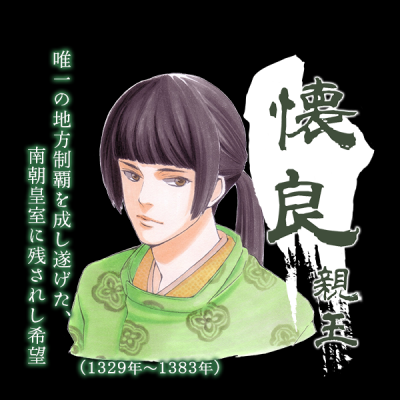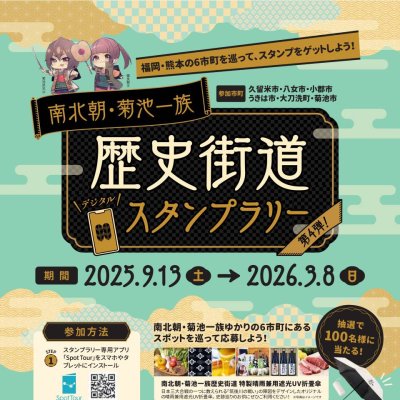懐良親王
 1348(正平3)年、当主となった武光は、後醍醐天皇の皇子である征西将軍懐良親王を菊池に迎えます。7歳で奈良の吉野を出発し、19歳の時に菊池入りを果たした懐良親王の使命は、味方をした武士たちの領地を約束することで、九州の南朝勢をまとめることでした。その懐良親王を菊池に迎えたことで、一族の中の、そして九州南朝勢の中の武光の立場は、ますますゆるぎないものになりました。戦の手腕に加え、政治的な才能も、武光の大きな強みと言えるでしょう。
1348(正平3)年、当主となった武光は、後醍醐天皇の皇子である征西将軍懐良親王を菊池に迎えます。7歳で奈良の吉野を出発し、19歳の時に菊池入りを果たした懐良親王の使命は、味方をした武士たちの領地を約束することで、九州の南朝勢をまとめることでした。その懐良親王を菊池に迎えたことで、一族の中の、そして九州南朝勢の中の武光の立場は、ますますゆるぎないものになりました。戦の手腕に加え、政治的な才能も、武光の大きな強みと言えるでしょう。
九州の南朝勢を納得させる大義名分を欲していた武光と、九州における強力な武力による後ろ盾が必要だった懐良親王。二人のニーズは完全に合致しており、それぞれの目的を果たすため、互いになくてはならない存在でした。
三つ巴の争い
この頃、北朝勢の中には異変が起きていました。中央における足利尊氏と弟の直義の対立に引きずられる形で、九州の北朝勢も2つの勢力に分裂していたのです。尊氏派の九州探題一色範氏と、直義派の足利直冬・少弐頼尚。これに懐良親王・武光の南朝勢が加わって、九州も3つの勢力が争いあう状況になりました。南朝にとっては大変幸運なことに、この時期の争いは北朝勢同士の戦いの方が中心で、互いを攻撃するために南朝勢と同盟関係を結ぶ、ということもしばしば起こっていました。
針摺原の戦い
1353(正平8)年、筑前の古浦城という城で、直義派の少弐頼尚が尊氏派の一色の勢力に取り囲まれる事態になりました。当時頼尚は武光と同盟関係にあったため、救援を求めました。武光はその時筑後に布陣していたのですが、ただちに一族の軍勢を率いて一色軍を撃破し、頼尚を救いました。
この戦いは「針摺原の戦い」と呼ばれ、この恩を受けて頼尚は「今より後、子孫七代に至るまで、決して菊池に弓を引くことはしません」と神に誓った血判状を武光に捧げました。
そしてこの血判状が、後に大きな役割を果たすことになるのです。