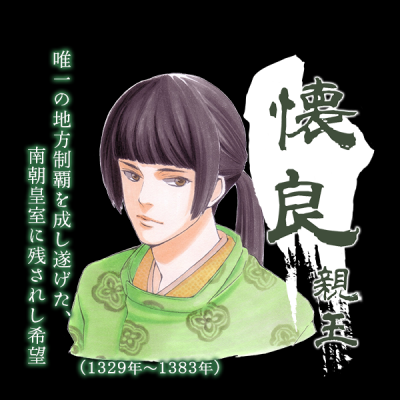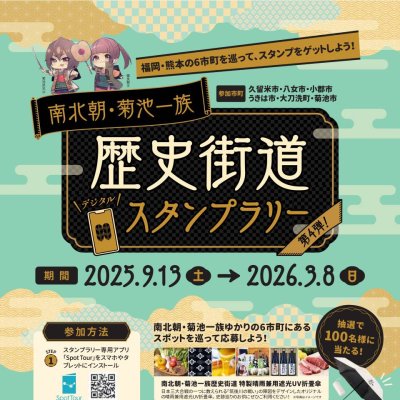1511(永正8)年、守山城に隈部親氏(ちかうじ)・長野運貞(よしさだ)・内古閑重載(うちこがしげとし)ら重臣たちが額を寄せ合う姿がありました。
23代政隆を退け当主となった武経でしたが、家臣の言葉にも耳を傾けることなく横暴な振る舞いが目立つため、多くの家臣の不興を買っていました。城内の険悪な雰囲気に身の危険を感じた武経は、ついに城を出て矢部に戻り旧名の阿蘇惟長に戻ってしまいました。
当主不在となった城で、重臣たちによって次の当主選びが行われていたのです。そこで白羽の矢が立ったのが、武澄の末裔である託麻武包(たけかね)です。この年、武包は所領の託麻郡本山城から守山城へ24(25)代当主として迎えられ、肥後守護の職に就きました。
 肥後の玉名地方も勢力下に収め、ますます勢力を伸ばしていく大友氏。一方、悲しいかな衰退の一途をたどる菊池氏。大友氏にとっては願ってもない好機到来、ここぞとばかりに圧力を強めます。
肥後の玉名地方も勢力下に収め、ますます勢力を伸ばしていく大友氏。一方、悲しいかな衰退の一途をたどる菊池氏。大友氏にとっては願ってもない好機到来、ここぞとばかりに圧力を強めます。
大友義長(よしなが)の死後、義鑑(よしあき)が跡を継いだ大友氏は、さらに強大な勢力となっていき菊池氏への干渉はいや増しに増していきました。義鑑の意をくんだ弟の重治(しげはる)は、武包を追い出すことを画策、菊池氏の重臣たちをそそのかし武包追放に成功します。
「当主の武包は、愚か者で役立たずじゃ。我こそが菊池の当主になるべきものだ!」
1520(永正17)年2月、守山城へ乗り込んだ重治は、自ら肥後守護と称し、菊池義宗(よしむね:後に義武(よしたけ)と改名)と名乗りを上げました。勢力が衰えた菊池氏には抗うすべもなく、これから以後、大友・阿蘇両氏が権勢をほしいままにしていきます。
菊池を追われた武包は、わずかな家臣とともに1523(大永3)年、筒が岳(玉名の小岱山)で挙兵しますが、強大な大友義鑑・阿蘇惟豊(これとよ)連合軍の前に屈するしかなく、島原の高来に逃れることとなりました。そして再び菊池の地を踏むこと叶わず、1532(天文元)年にこの地で生涯を閉じたのでした。
一方、武包を追放した義宗は、大友氏の後ろ盾で当主の座を手に入れたにもかかわらず、兄義鑑の指図にも従わないほど高慢で粗暴な性格、わがままな生活を続けていました。見かねた菊池一族の木野親則(きのちかのり)がたびたび忠告するのですが、聞く耳を持ちません。あろうことか、ついには親則を手討ちにしてしまいます。主君のためを思い進言する忠臣を斬り捨てるとはなんたる蛮行、家臣たちの心を離れさせるには十分すぎる振る舞いでした。家臣たちは、次第に義宗をないがしろにするようになっていきます。城内のただならぬ雰囲気に身の危険を感じた義宗(この頃、義武と改名)は、1534(天文3)年、相良義滋(よししげ)を頼って八代へと逃れ、様子を見ることとしました。
そこへ現れたのが、隈本城主の鹿子木鑑員(かのこぎあきかず)。菊池一族の老臣田島宗以(たしまそうい)たちと図り、八代に逃れた義武を隈本城へ迎え、1550(天文19)年8月、菊池家復興の兵を上げました。
丁度この頃、豊後の大友氏には、義鑑が臣下に殺されるという大事件が起こります。後を継いだのは嫡子の義鎮(よししげ:後の宗麟(そうりん))。すぐさま小原鑑元(あきもと)・佐伯惟教(これのり)に2万といわれる大軍を与え、隈本城へと向かわせました。義武軍は防戦するも敗退、わずか百騎程の兵に守られた義武は、金峰山から河内、さらには海を隔た肥前の島原へと落ち延びていきました。
その後、相良晴広(はるひろ)を頼って人吉へ入った義武でしたが、義鎮の追及の手は緩みませんでした。
「これ以上、相良に迷惑はかけられぬ。我は豊後へと参ろう。晴広殿、妻子を頼み申した。」
相良氏への再三の身柄の引き渡しの要求に、義武は覚悟を決めます。1554(天文23)年、11月15日、嫡男の高鑑(たかあき)を伴って豊後へと赴きます。24日、直入郡の山中で捕えられ自刃して果てました。時に51歳でありました。
ここに菊池氏の肥後の支配は終焉を迎えます。これ以後、肥後は名実ともに大友氏の支配下に置かれることとなったのです。