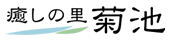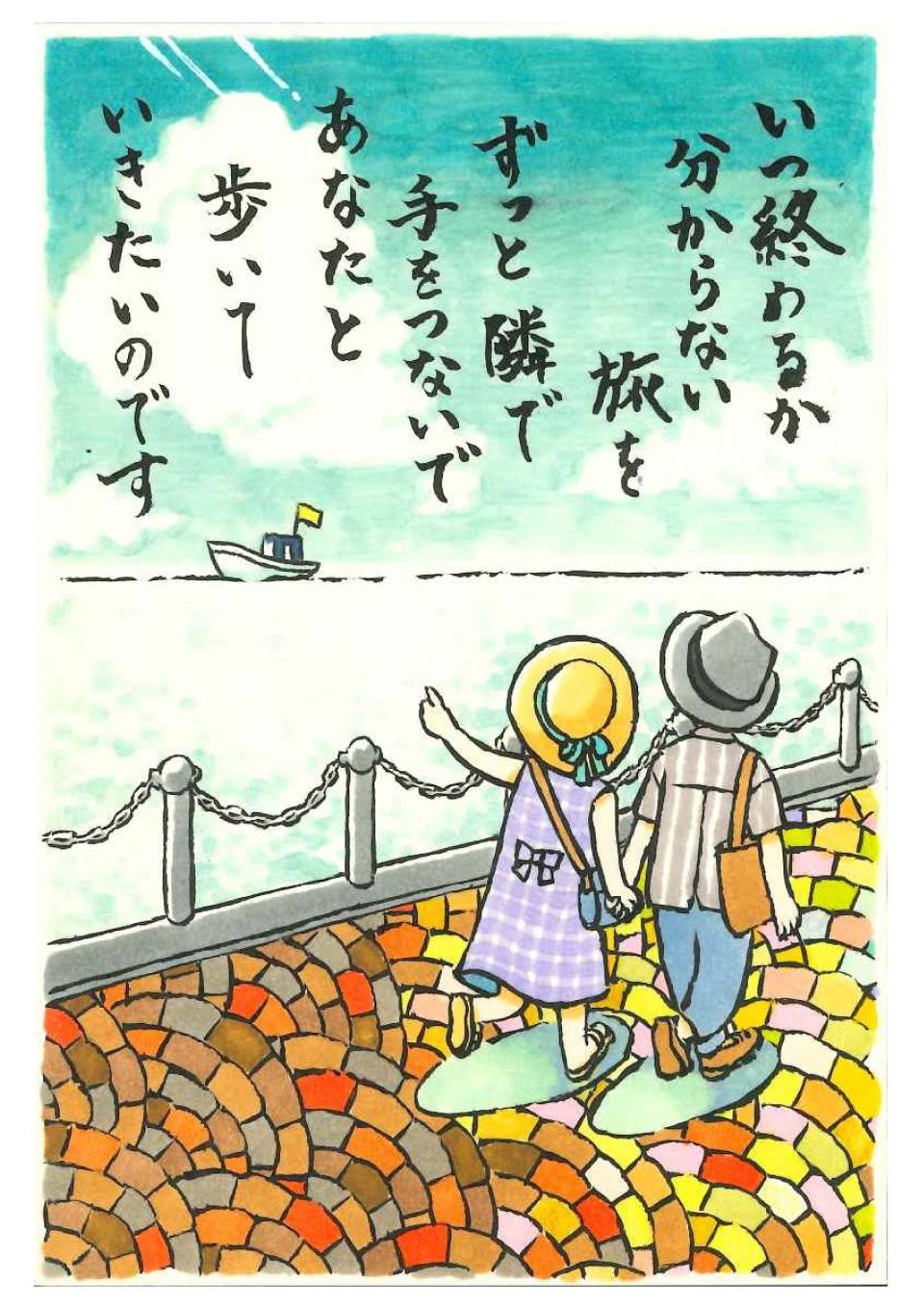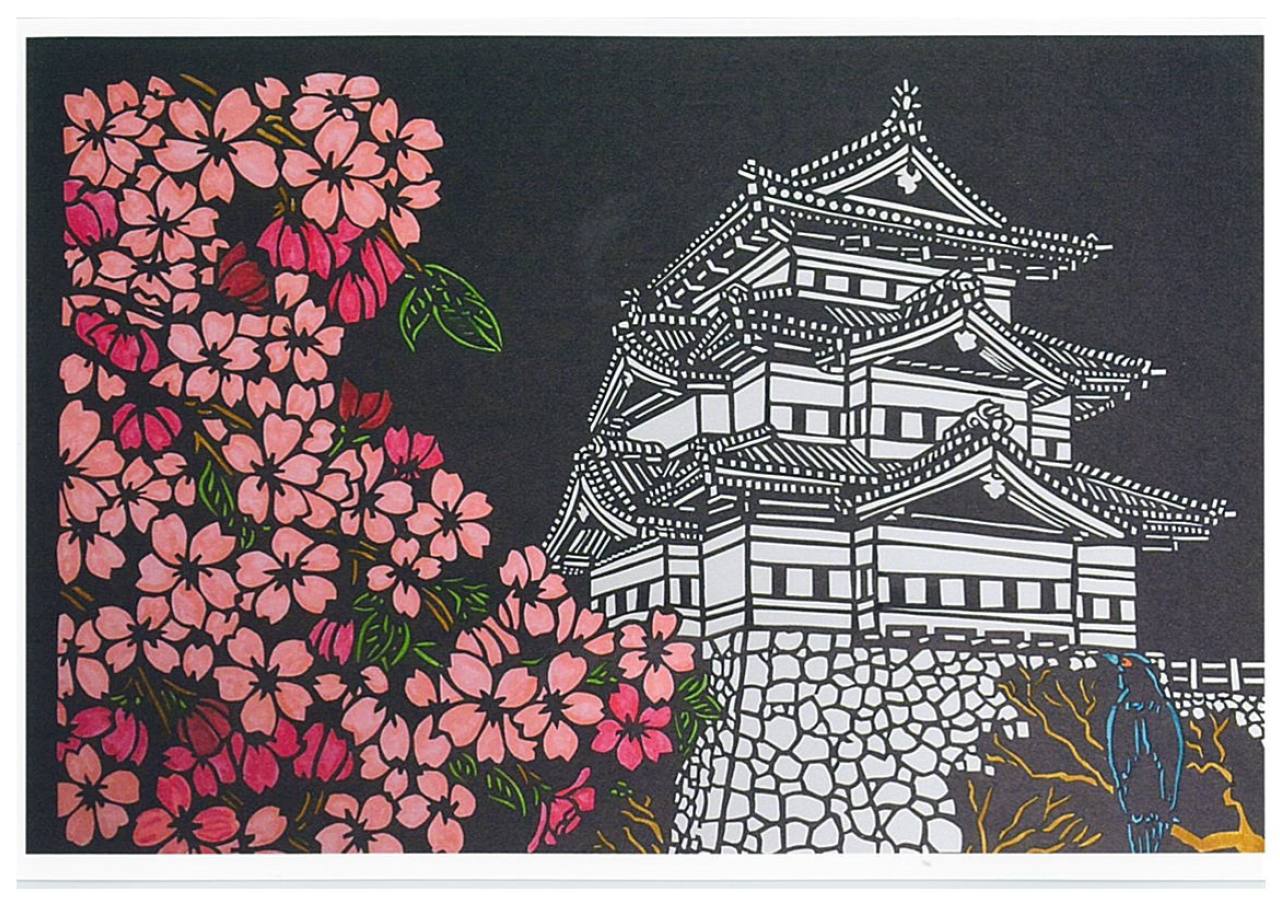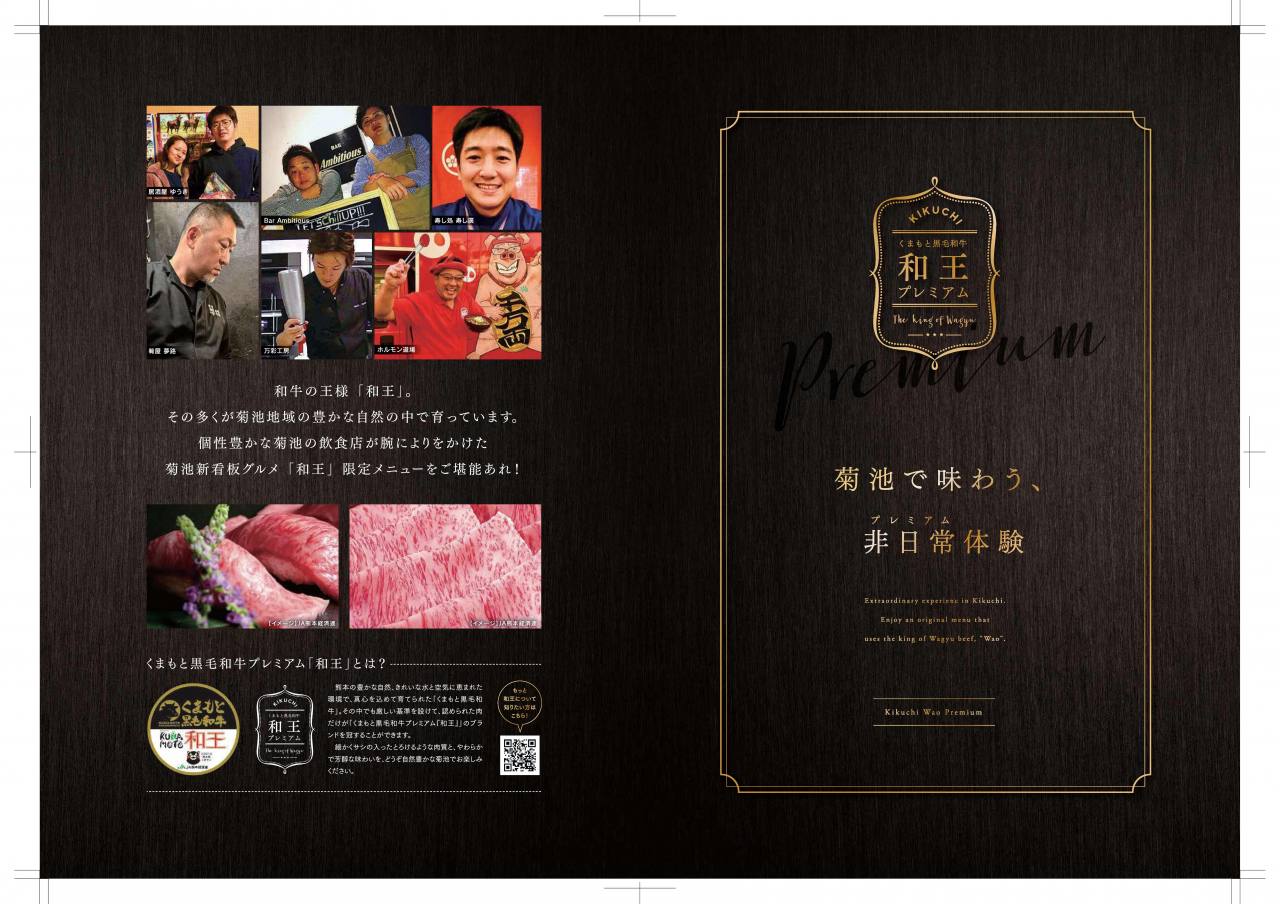緊急情報はありません
- 菊池市の概要
「菊池市の概要」の内容
- 菊池市の紹介
- 庁舎・施設案内
- 連絡先
- 各種申請書・様式
- 各種補助金・奨励金
- 各種相談
- 各種計画
- 各種募集
- 生活情報
「生活情報」の内容
- まちづくり
- 健康・医療・戸籍・年金
- 妊娠・出産・子育て
- 障がい・福祉・高齢者・介護保険
- くらし・上下水道・生活環境
- ごみ・リサイクル
- 市税
- 商工農林畜産業
- 教育・生涯学習
- 外国人生活情報
- 観光情報
「観光情報」の内容
- トピックス
- 遊ぶ
- 食べる
- 泊まる
- 学ぶ
- 移住定住
「移住・定住」の内容
- 菊池市のご紹介
- お知らせ
- 空き家バンク
- 新菊池人の声
- お試し住宅
- しごとの情報
- 子育ての情報
- 暮らしの情報
- 移住・定住支援制度
- 市政情報
「市政情報」の内容
- 選挙
- 監査委員
- 公平委員会
- 人権教育
- 男女共同参画社会
- 指定管理者制度
- マイナンバー制度
- 情報公開・個人情報保護
- 人事・給与
- 職員採用
- 財政
- 行政改革
- 入札情報
「入札情報」の内容
- 入札公告
- 入札結果
- 入札に関するお知らせ
- 条例等
- 様式
- その他(入札情報)