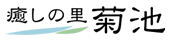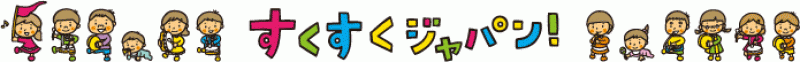子ども・子育て支援新制度について
1.子ども・子育て関連3法について
国では、急速な少子化の進行、家庭と地域を取り巻く環境の変化に対応するために、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ども・子育て支援の充実を目的として「子ども・子育て関連3法」を平成24年8月に制定しました。
菊池市では、この「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」の平成27年4月からの実施に向けて、「菊池市子ども・子育て支援事業計画」を策定するとともに、「各種施設・事業の設備・運営の基準等」について、条例等によりこれを定めました。
子ども・子育て関連3法
- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部改正
- 子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2.新制度のポイント
(1)認定こども園・幼稚園・保育所への共通の給付
これまでの施設によって異なる運営費の給付体系を一本化するとともに、子どもが減少傾向にある地域の保育機能を確保します。
(2)認定こども園制度の改善
幼保連携型認定こども園の認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として位置づけます。
(3)地域の実情に応じた子ども・子育て支援
教育・保育施設を利用する子どもだけでなく、在宅等のすべての子どもを対象として、地域子育て拠点施設や放課後児童クラブなどの事業を充実させます。
(4)地域のニーズに基づいた計画を市町村が実施
市町村のニーズに基づいた計画を策定し、事業を実施します。
(5)社会全体による費用負担
子ども・子育て支援を実現するために、消費税率の引き上げにより、恒久的な財源を確保します。
(6)子ども・子育て会議の設置
市町村のニーズに基づいた計画を策定するために、市町村版子ども・子育て会議を設置します。
3.子ども・子育て支援法に基づく基準条例等の制定について
子ども・子育て支援新制度において、子ども・子育て関連3法に基づき、市町村は条例による基準を制定する必要があります。
この基準とは、認定こども園や保育所などを利用する子どもの身体的・精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するための基準です。(施設で勤務する職員の資格要件や配置基準、保育室の床面積や給食設備の基準など)
これらの基準を菊池市において条例で定める場合には、国が法令で定める「従うべき基準(※)」と「参酌すべき基準(※」に沿って定めることが、子ども・子育て関連3法によって義務付けられています。
本市が条例等で定めるべき基準は、以下のとおりです。
- 小学校就学前の子どもに係る保育必要量の認定基準・・・制定済み
- 認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育事業(※)の運営に関する基準・・・制定済み
- 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準・・・制定済み
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準・・・制定済み
- 子ども・子育て会議の設置に関する条例・・・・・制定済み
※「従うべき基準」
条例の内容を直接的に拘束する必ず従わなければならない基準。ただし、地域の実情に応じて基準を上回る定めを許容されるもの。
※「参酌すべき基準」
地方自治体が十分参酌した結果としてあれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるもの。
※「特定地域型保育事業」
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
平成26年9月及び12月菊池市議会において、各基準条例が制定され、平成27年4月から施行されることになりました。
- 菊池市小学校就学前の子どもに係る保育必要量の認定基準を定める条例
- 菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
- 菊池市家庭的保育事業等の運営に関する基準を定める条例
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準条例
(1)小学校就学前の子どもに係る保育必要量の認定基準
- 子ども・子育て支援新制度では、実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、国の基準に基づき、保育の必要性を認定する仕組みとなります。
- 認定に当たっては、(1)「事由(保護者の就労、疾病など」、(2)「区分(保育標準時間、保育短時間の2区分あり」について、国が基準を設定しています。
- 市町村は、子ども・子育て支援法第20条第3項に基づき、この基準を条例化(規則・要綱でも可)することが必要です。
| 年齢 | 保育の必要性 なし | 保育の必要性 あり |
|---|---|---|
3歳以上 | 1号認定 教育保育標準時間認定(4時間) 【利用する教育・保育施設】
| 2号認定 保育認定 【利用する教育・保育施設】
|
| 3歳未満 | 認定なし 【利用する教育・保育事業】
| 3号認定 保育認定 【利用する教育・保育施設】
|
1号認定・・・満3歳以上で、教育を希望される場合(幼稚園・認定こども園)
2号認定・・・満3歳以上で、「保育の必要性」があり、保育所等を希望される場合(保育所・認定こども園)
3号認定・・・満3歳未満で、「保育の必要性」があり、保育所等を希望される場合(保育所・認定こども園・地域型保育事業)
| 項目 | 現行 (H26年度) | 国基準 (H27年度~) | 菊池市基準 (H27年度~) |
|---|---|---|---|
| 事由 |
※ 就学、虐待・DVのおそれなど |
| 国の基準どおり |
| 区分 |
※1ヶ月は4週とする |
※保護者や家庭の状況を考慮して事業者が定める。 |
|
(2)認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
- 子ども・子育て支援新制度では、「認定こども園・幼稚園・保育所」の設置者及び「特定地域型保育事業」の事業者は、市町村が定める運営の基準を遵守しなければならないこととされています。
- 運営の基準には、(1)「利用定員」、(2)「利用開始に伴う基準」、(3)「教育・保育の提供に伴う基準」、(4)「管理運営等に関する基準」があり、国が基準を設定しています。
- 市町村は、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項に基づき、この基準を条例化することが必要です。
(3)家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
- 子ども・子育て支援新制度では、認定こども園・幼稚園・保育所に加えて、市町村による認可事業である家庭的保育事業等(家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業)※があり、きめ細かい保育を実施することが想定されています。
- 家庭的保育事業として認可される基準には、(1)「共通の基準」及び(2)「事業別の基準」があり、国が基準を設定しています。
- 市町村は、児童福祉法第34条16に基づき、この基準を条例化することが必要です。
※家庭的保育事業等
- 家庭的保育事業・・・・保護者の居宅等で行われ、家庭的な雰囲気の下、きめ細かな保育を実施(1人以上5人以下)
- 小規模保育事業・・・・施設内で行われ、保育士・保育従事者・家庭的保育者などにより保育を実施(6人以上19人以下)
- 居宅訪問型保育事業・・保護者の自宅等で行われ、1対1を基本とするきめ細かな保育を実施(1人)
- 事業所内保育事業・・・企業等が主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもに保育を提供
(4)放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
- 子ども・子育て支援新制度では、保護者就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、学校の授業の終了後、適切な遊び・生活の場を与え、その健全な育成を図る「放課後児童健全育成事業」があります。
- この放課後児童健全育成事業については、その「設備及び運営」について国が基準を設定しており、市町村は児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づき、この基準を条例化することが必要です。
4 菊池市子ども・子育て支援事業計画について
子ども・子育て関連3法に基づき「菊池市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたっては、国の「子ども・子育て支援事業計画基本指針」に沿って、記載事項の内容を検討していくことになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区域の設定 | 量の見込みや、確保方策を設定する単位として、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域(「教育・保育提供区域」)を設定する。 ※1市町村1区域、旧市町村単位、小学校区、中学校区など |
| 認定こども園・幼稚園・保育所の量の見込み、確保の内容及び実施時期 | 区域ごとに、量の見込み(必要利用総数)を定める。 ※現在の利用状況 + 利用希望 区域ごとに量の見込みに対応するための受入れ枠の確保策及びその時期を定める。 ※「量の見込み」と「現在の受入れ枠」での不足分をどうやって、いつまでに補うか |
| 特定地域型保育事業の量の見込み、確保の内容及び実施時期 | 区域ごとに、量の見込み(必要利用総数)を定める。 ※現在の利用状況 + 利用希望 区域ごとに量の見込みに対応するための受入れ枠の確保策及びその時期を定める。 ※「量の見込み」と「現在の受入れ枠」での不足分をどうやって、いつまでに補うか |
| 認定こども園の設置数・時期、普及のための考え方 | 認定こども園を普及させる背景や必要性等を定める。 幼児期の学校教育・保育と小学校教育との円滑な接続(幼保小連携)の取り組みの推進を定める。 |
5 子ども・子育て支援に関するアンケート調査
また、「菊池市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたっては、ニーズに基づいた計画とするために、就学前児童の保護者を対象に、「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」を実施しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 配布方法 | 幼稚園・保育園等を通じた配布または郵送による配布 |
| 回収方法 | 幼稚園・保育園等を通じた回収または郵送による回収 |
| 抽出方法 | 末子を対象として、全数調査 |
| 調査時期 | 平成25年11月に実施 |
| 配布数 | 2,089件 |
| 有効回答数 | 823件 |
| 有効回答率 | 39.4% |
6 菊池市子ども・子育て会議
菊池市のニーズに基づいた計画とするために、児童福祉に精通した有識者により構成される「菊池市子ども・子育て会議」のご意見を伺いながら策定しています。
| 番号 | 担当分野 | 所属 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保育所 | 菊池市保育協議会 副会長 菊池みゆき保育園 園長 | 福田 俊彦 |
| 2 | 幼稚園 | 菊池幼稚園 園長 | 横田 輝雄 |
| 3 | 子育て支援全般 | 菊池市社会福祉協議会 福祉課長 | 青木 輝彦 |
| 4 | 子育て支援拠点事業 | 菊池市社会福祉協議会 福祉課地域福祉係 | 村上 智子 |
| 5 | 放課後児童クラブ | 特定非営利活動法人 未来への希望 理事 | 吉田 崇 |
| 6 | 小中学校保護者 | 菊池市PTA連絡協議会 | 岩根 貴史 |
| 7 | 地域福祉 | 菊池市民生委員児童委員協議会連合会 監事 | 右田 美喜江 |
| 8 | 教育 | 菊池市教育委員会 学校教育指導員 | 末田 稔 |
| 9 | 青少年育成 | 菊池市青少年育成市民会議 会長 | 前川 薫 |
| 10 | 母子保健 | 菊池市母子保健推進委員 代表 | 御書 典子 |
| 11 | 障がい者福祉 | 児童発達支援センター輝なっせ 児童発達支援管理責任者 | 松本 真由美 |
| 12 | 男女共同参画 | 菊池市男女共同参画審議会 委員 | 内田 利美 |
| 13 | ひとり親家庭 | 菊池市母子寡婦福祉連合会 会長 | 生田 喜利子 |
| 会議名 | 日時・場所 | 会議資料 |
|---|---|---|
第1回 菊池市子ども・子育て会議 | 平成26年7月16日(水) 午前10時~ 菊池市福祉会館2F 大研修室 | |
| 第2回 菊池市子ども・子育て会議 | 平成26年8月21日(木) 午前10時~ 菊池市役所3F 大会議室 | |
| 第3回 菊池市子ども・子育て会議 | 平成26年10月14日(火) 午後2時~ 菊池市役所3F 大会議室 | |
| 第4回 菊池市子ども・子育て会議 | 平成27年2月9日(月) 午後1時30分~ 菊池市福祉会館2F 大研修室 | |
第5回 菊池市子ども・子育て会議 | 平成28年3月25日(金) 午後1時30分~ 七城公民館2階 中研修室 | !!NEW!! |
よくある質問Q&A
幼稚園等
- 幼稚園等に直接利用申込みをします
- 幼稚園等から入園の内定を受けます
- 幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します
- 幼稚園等を通じて市から認定証が交付されます
- 幼稚園等と契約をします
保育所等
- 市に「保育の必要性」の認定を申請します
- 市から認定証が交付されます
- 保育所等の利用希望の申込みをします
- 申請者の希望、保育所等の状況などにより、市が利用調整をします
- 利用先の決定後、契約となります
※ 認定こども園を利用する場合は、1号認定の場合は青枠の、2号・3号認定の場合は赤枠の手続の流れが基本となります。
新制度の利用にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払いが基本となります。
新制度のさまざまな支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が定める基準を上限として、市が地域の実際の状況に応じて定めることになります。
契約・支払先は、利用する施設によって異なります。
認定こども園・幼稚園・公立保育所等を利用する場合
利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育所の場合は市へ)支払います。
私立保育園を利用する場合
利用者は市と契約し、保育料を市へ支払います。