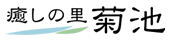菊池市稗方では、毎年12月20日「嫁とり祭り」と呼ばれる民俗行事がおこなわれています。
午前中、村社である稗方菅原神社で神事と次の年の座元決めがおこなわれ、午後から座元の家に場所を移して、神前形式による仮の結婚式がおこなわれます。地域の家内安全、子孫繁栄などを願っておこなわれる行事です。
ネコボクを敷き、その周囲を幕で囲って式場を設営します。進行役は神社の神職で、媒酌人を座元組の幼児が務めます。三々九度の杯を交わし、ひととおりの式が終了すると進行役の神職が「この婚礼はネコボクのうえのことまで」と発し、出席者全員の笑い声のなかで直会となります。
いつごろから始められたかははっきりしませんが、区に伝えられる文書によれば、少なくとも江戸時代の終わり頃にはおこなわれていたことが分かっています。
地域の言い伝えでは、菅原道真が旅の途中に稗方に立ち寄ったとき、喉が渇いたので酒を所望したところちょうど近くで結婚式がおこなわれていたので、めでたいとのことで道真がその酒を振舞った、というのが由来であると伝えられています。
 嫁とり祭りの様子。ネコボクの上にござを敷き、笹竹を立てて幕で囲って式場を造ります。
嫁とり祭りの様子。ネコボクの上にござを敷き、笹竹を立てて幕で囲って式場を造ります。
 前半の神事等がおこなわれる菅原神社。優れた地元石工がいたようで、正面の石像ほか境内に梅の石造品もあり、特徴的なものが多いです。
前半の神事等がおこなわれる菅原神社。優れた地元石工がいたようで、正面の石像ほか境内に梅の石造品もあり、特徴的なものが多いです。