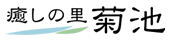菊池市では、手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解を深め、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進を図ることにより、障がいのある人もない人も、すべての市民がお互いの人格と個性を尊重しながら、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指し、本条例を制定しました。
現在実施している、本庁舎への手話通訳者の配置(月2回)や公民館での手話講座などの事業は引き続き行うとともに、今後は市民の皆様のご意見を聞きながら、ニーズに応じた施策を進めていく予定です。
※令和7年3月菊池市議会定例会において条例可決後に、熊本県ろう者福祉協会及び手話サークルの皆様と記念撮影を行いました。
条例の概要
【目的】(第1条)
手話が言語であるという認識に基づく手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する基本理念を定め、市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにし、市の施策を推進することで、全ての市民が安心して暮らすことができる共生社会の実現を目的とする。
【定義】(第2条)
「ろう者」、「障がい者」、「事業者」、「障がいの特性に応じたコミュニケーション手段」、「合理的な配慮」の用語を定義。
【基本理念】(第3条)
・手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、障がいの有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し合うことが重要であるとの認識の下に行うこと。
・手話言語の普及は手話が独自の文法体系を有する言語であって、ろう者が日常生活や社会生活を営むために大切に受け継いできたものであるという認識の下に行うこと。
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進は、その手段を障害者自らが選択し、利用できることの重要性を市民及び事業者が理解した上で、その選択の機会の確保及び利用の拡大を図ること。
【市の責務】(第4条)
・基本理念に基づき、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進すること。
・事務又は事業実施に当たり、必要かつ合理的な配慮を行うこと。
【市民の役割】(第5条)
・基本理念への理解を深め、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めること。
【事業者の役割】(第6条)
・基本理念への理解を深め、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるとともに、事業実施にあたっては必要かつ合理的な配慮を行うこと。
【施策の推進】(第7条)
・市は次に掲げる施策を推進する。
1.手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策
2.障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の提供に関する施策
3.障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関する施策
4.障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を支援する者の確保及び養成に関する施策
5.その他、この条例の目的を達成するために必要な施策
条例の全文
菊池市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(PDF 約59KB)
菊池市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(WORD 約25KB)
(ルビあり)菊池市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(PDF 約565KB)
(白黒反転表示)菊池市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(WORD 約25KB)