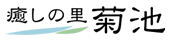令和7年10月30日(木)に開催した第4回ヘルスメイト養成講座では、「お口の健康」と「全世代の食育」をテーマに、健康寿命の延伸に欠かせない学びを深めました。全7回の講座のうち4回目となる今回は、歯科衛生士と管理栄養士から、毎日の生活に直結する重要な知識が共有されました。
お口の中をのぞいてみよう!~歯周病と正しい歯の磨き方~
健康の土台「歯」の大切さ
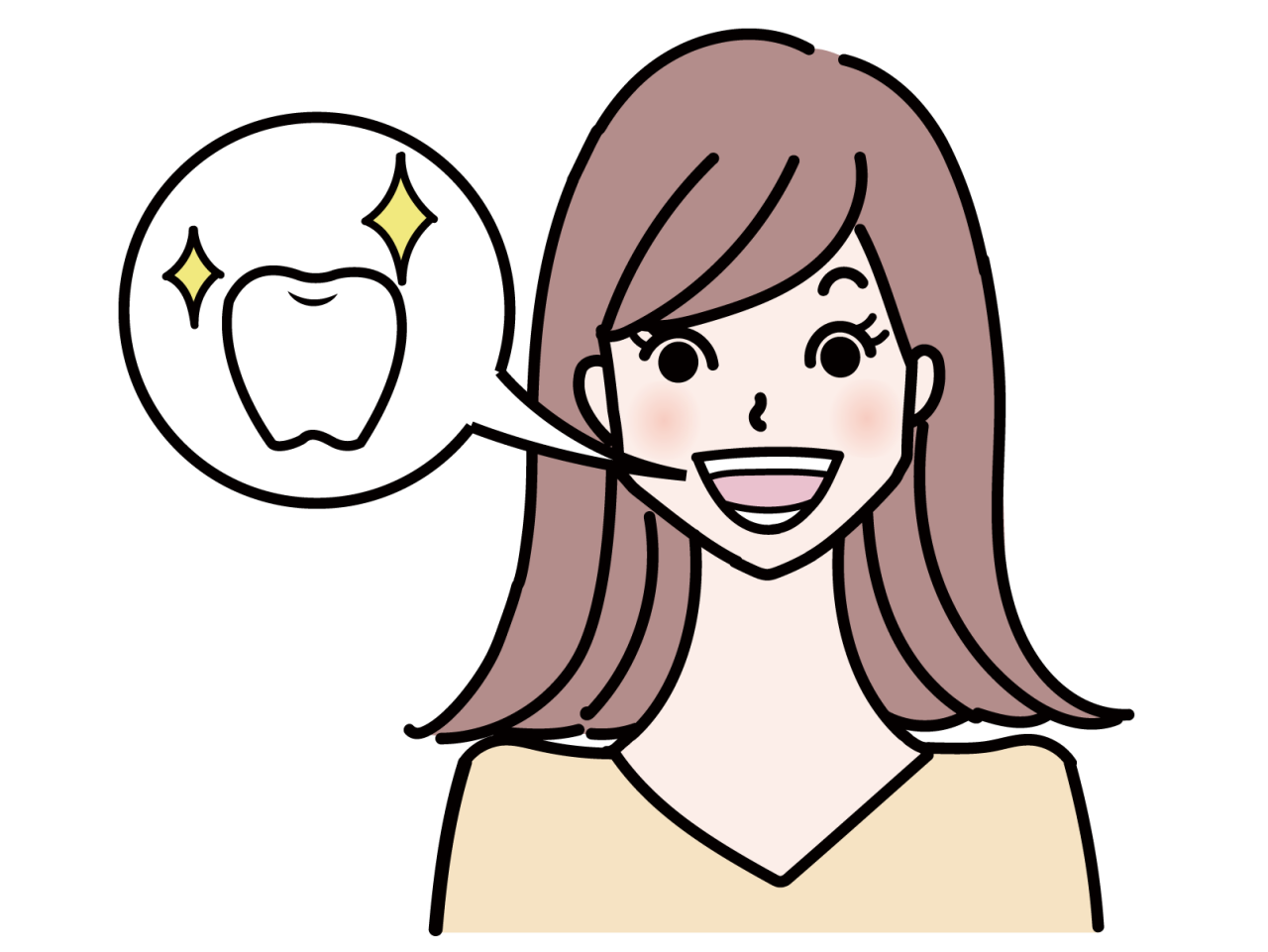 健康で自立した生活を送る期間を示す健康寿命には、食事と、それを支える「口」の健康が不可欠です。歯は、噛む、話す、表情を作る、さらには脳の活性化や全身の健康にまで深く関わっています。
健康で自立した生活を送る期間を示す健康寿命には、食事と、それを支える「口」の健康が不可欠です。歯は、噛む、話す、表情を作る、さらには脳の活性化や全身の健康にまで深く関わっています。
歯を失う最大の原因は、むし歯ではなく「歯周病」です。これはギネスブックにも「世界で最も一般に蔓延している感染症」と記されるほど身近な病気です。歯周病は、歯垢内の細菌が歯茎の奥に進み、歯を支える骨を溶かし、最終的に全身の様々な疾患(糖尿病、心疾患、妊婦の早産・低体重児など)のリスクを高めます。
歯周病予防と生活習慣
歯周病の発症には、細菌、外傷性因子、宿主(抵抗力)、環境因子(生活習慣)の4つの因子が重なっており、日頃の予防が鍵となります。特に喫煙は歯周病を悪化させることが分かっています。また、鼻呼吸を意識することや、自分に合った正しい歯磨きを習得することも非常に重要です。
よく噛むことの驚きの効果
現代人の咀嚼回数は弥生時代の約6分の1(約600回)に減少していると言われています。「ひみこの歯がいーぜ」を合言葉に、よく噛むことの効果を意識しましょう。
• ひ…肥満予防
• み…味覚の発達
• こ…言葉の発音はっきり
• の…脳の発達
• は…歯の病気予防
• が…ガン予防
• いー…胃腸快調
• ぜ…全力投球
参加者からは、「歯周病が全身疾患のリスクになることが分かり、検診の必要性を感じた」「磨き方をさっそく実行したい」との声が寄せられました。
全世代の食育(学童期・思春期、高齢期)
学童期・思春期の食育~貧血にならないために~
心身の発達が著しい学童期・思春期の食生活の乱れ(朝食の欠食、間食の摂りすぎなど)は、一生の健康の基礎を脅かします。特に朝食は、体温を上げ、脳を活性化させ、集中力を高める最も重要な食事です。
思春期の女子に多い鉄欠乏性貧血の予防には、レバーや小松菜などの鉄を含む食品と、吸収を助けるビタミンCやたんぱく質の組み合わせが効果的です。
高齢期の食育~フレイル予防のために~
高齢期の健康を考える上で重要なのが、「フレイル(虚弱)」「サルコペニア(筋肉減少)」「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」です。特にフレイルは健康と要介護の中間段階であり、食事、身体活動、社会参加の三本柱で予防・回復が可能です。
高齢者は食欲低下や孤食などから「低栄養」に陥りやすく、筋力や免疫力の低下を招きます。フレイル予防の食事の基本は、バランスの良い3食です。
• 意識的なたんぱく質摂取:魚、肉、卵、大豆製品をしっかり摂る。
• 10食品群のチェック:「さあ、にぎやかにいただく」(魚、肉、卵、大豆、牛乳、油、芋、海藻、野菜、果物)を意識。
• 共食の勧め:家族や仲間と食卓を囲む「共食」は、心の栄養にもつながります。
受講者からは、「朝食の大切さを再確認し、空腹の時間を延ばさないようにしたい」「フレイル予防のため、たんぱく質とバランスの良い食事を心がける」など、具体的な行動につながる感想が聞かれました。
次回のヘルスメイト養成講座は11月に開催予定です。 今回の学びを日々の生活に活かし、一緒に健康長寿を目指しましょう!