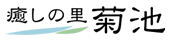熊本県は「腎不全の患者一人当たり医療費が高い」「慢性透析患者数が全国ワーストクラス」「新たに透析導入した患者の原因疾患は糖尿病性腎症が一番多い」という特徴があります。糖尿病性腎症を知って腎不全(透析)を予防しましょう。
糖尿病って?
糖尿病とはインスリン(血糖値を下げるために働くホルモン)の働きが弱まったり、十分に分泌されなくなったりすることで血糖値が高くなる病気です。糖尿病になっても、初期の場合は、自覚症状がないこともあります。糖尿病は、病気になってから早い時期に治療を始めることが病気の進行や合併症の予防にとって重要です。
糖尿病を治療しないとどうなる?
糖尿病により、血糖値の高い状態が長く続くと、血液中のブドウ糖が血管や神経に悪影響を及ぼします。
細い血管が傷ついて起こる合併症には、神経の合併症(糖尿病性神経障害)、眼の合併症(糖尿病性網膜症)、腎臓の合併症(糖尿病性腎症)などがあります。
太い血管が詰まって起こる合併症には、動脈硬化があり、動脈硬化が進行すると、心臓の血管や脳の血管が詰まり心筋梗塞や脳梗塞などが起こります。足の血管が詰まる抹消動脈疾患などもあります。
糖尿病性腎症ってなに?
糖尿病によって起こる腎臓の合併症のことです。明らかな腎障害がある場合、あるいは腎機能が低下した状態が3か月以上続く病気を「慢性腎臓病(CKD)」といいます。この中で、糖尿病であり、蛋白尿が確認されてから腎機能が低下するものを「糖尿病性腎症」といいます。糖尿病性腎症は、急に尿が出なくなるのではなく、段階を経て病気が進行します。そのため、できるだけ早期に発見し、適切な治療をすることが重要です。
慢性腎臓病(CKD)が重症化すると、透析が必要になりますが、原因疾患別に分けると糖尿病性腎症が一番多いです。糖尿病の治療を放置し、血糖値が高い状態が長く続くと、腎機能は低下し、10-15年経過したころには透析治療が必要な状態になりうるといわれています。
糖尿病性腎症の病気分類
病期 | 尿たんぱく値(g/gCr)あるいはアルブミン値(mg/gCr) | 腎機能・GFR(ml/分/1.7㎡) | 有効な治療法 |
第1期(腎症前期) | 正常(30未満) | 30以上 | 血糖コントロール |
第2期(早期腎症期) | 微量アルブミン尿(30~299) | 30以上 | 厳格な血糖コントロール、降圧治療 |
第3期(顕正腎症期) | 顕性アルブミン尿(300以上)あるいは持続性タンパク尿(0.5以上) | 30以上 | 厳格な血糖コントロール、降圧治療、タンパク質制限 |
第4期(腎不全期) | 問わない | 30未満 | 降圧治療、低タンパク食、透析療法導入 |
第5期(透析療法期) | 透析療法中 | 透析療法、腎移植 | |
第1期・第2期は自覚症状はほとんどありません。尿の検査をしないと判断ができません。
第3期以降では、進行を遅らせることはできても、良い状態に戻すことはできないため、第2期の段階で糖尿病性腎症を見つける必要があります。早期発見のために健診を受けることが大切です。
合併症を予防しましょう
糖尿病性腎症を予防するためには、糖尿病の予防もしくは糖尿病の治療を継続することが大切です。以下のことに取り組みましょう。
◇ 生活習慣病健診、特定健診、後期高齢者健診など健診を毎年受ける
◇ 定期的に診察や検査を受ける(治療を中断しない)
◇ 血糖値、血圧、コレステロール、体重を医師の指示の範囲で維持する
◇ 生活習慣を見直す(食事や運動など)
◇ たばこを吸っている場合はたばこをやめる