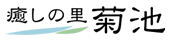「コロナ ~今、何が起きているのか~」
地域人権教育指導員
宮川伊十(みやがわいじゅう)
誰にも予測できなかった新型コロナウイルスの脅威。国境や国力・文化等に関係なく、瞬く間に世界中に拡散し、多くの犠牲者を出しています。
コロナウイルスへの恐怖
我が国においても、4月16日に「緊急事態宣言」が全都道府県下に出され、社会活動・経済活動・文化活動までが自粛に追い込まれました。「不要不急の外出をしない」・「密閉・密集・密接を避ける」の通達が浸透し、街や通りから人が消えました。また、「自分が感染源になったらという不安」も生活に大きな制約を加えました。
学校においては、2月後半から校内行事等が自粛となり、節目となる卒業式・入学式は当事者・保護者だけの出席という異例の形でどうにか執り行われました。そして、全学校に対するいきなりの一斉休校措置。休校は、5月末までの約3ヶ月にわたり、学校での学び合い、友だちとの遊び、大好きな給食が子どもたちの生活から消えました。
「口惜しやコロナ一色春が過ぎ」
せせらぎ俳句会
森正子(もりまさこ)
出かけることもできず、季節の移ろいを愛でることもできません。今、子どもたちの声 、当たり前の生活が徐々に戻り始めました。
コロナウイルスがもたらす災い
私たちは、新型コロナウイルス感染症の問題を、「他人事」「よそ事」と捉えていなかったでしょうか。全国的な感染拡大が広がると様々な問題が起きてきました。
- 感染源となった人の行動や人間性への誹謗・中傷
- 消毒液、マスク等の買い占め・転売、品不足
- 規制を守って営業する飲食店へのいやがらせ
- 医療従事者等及びその家族への深刻な差別・排除行為 等々。
人のつながりを紡ぎ直す
自粛やテレワークが、日常生活を見直す機会にもなりました。
- 誰にでも感染。「感染源となった人が悪いのではなく、ウイルスが悪い」という考えの広がり
- 「マスクがなければ作ればいい」と、工夫を凝らした手作りマスクの登場
- コロナと最前線で闘う医療従事者に対して「感謝の心」を表す「ライトイットブルー」(建物等を青色に照らす運動)の広がり
- 家庭で過ごす時間が増えたことで、不安を共有したり、家族の絆を確認する機会となる
中国から届いたマスク
本市に、数多く届けられたマスクの中に、元中国遼寧(りょうねい)省農牧業庁職員の郭錦生(かくきんせい)さんから贈られた1500枚のマスクがあります。
昭和15年、泗水町の岩下隆弘(いわしたたかひろ)さんらを中心に同省瀋陽(しんよう)市に渾河(こんが)開拓団として、入植しました。日本から持ち込んだ優れた農業技術と相互信頼関係で、他にない農場を創りあげます。終戦時も危害を加えられることなく、無事帰国することができました。この農場は、その後、中国の模範農場となり、国家再建にも貢献します。27年後の国交正常化後、岩下俊一(いわしたしゅんいち)さんら二世の人たちが待望の交流を始め、その橋渡しをしたのが郭さんでした。
彼の「たとえ国と国との関係が壊れても民間の交流に戸は立てれない」の言葉が、今も生きており、その思いのこもった中国からのマスクです。コロナにより、私たちは多くのことを学ばされ、今、地球規模で新たなしくみや日常が生まれつつあります。 (※菊池広報6月号参照)