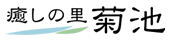自分らしく安心してくらせる地域
以前、学校に勤務していたときのことです。正門横で朝の交通見守りをしていると、一人の男子中学生が、高齢の女性に寄り添うように歩いて登校している姿を見ました。その女性が手にしているのは、ティッシュボックスと杖代わりの木の枝。どう見ても、散歩している姿には見えません。その男子中学生もきっと、その姿から「何かへんだな」と思ったに違いありません。その後、近くにいた先生と話をして、すぐに女性を預かって、いったん学校で対応することにしました。
その生徒にどうして一緒にいたのか尋ねると、「ちょっとおばあさんが気になったので、とりあえず一緒に歩いてきました」という返答でした。こちらからも「よく寄り添ってくれたね。ありがとう」と礼を言いました。
後で分かったことですが、女性は学校職員の知り合いだったので、事なきを得ることができました。もし、誰も近くで見守る人がいなかったら、その高齢者を見過ごすことになったかもしれません。
温かい目で見守る
市内小中学校では、授業の一環として認知症サポーター養成講座を受講しています。そのねらいとして、次のようなものが挙げられます。
- 認知症に対して、正しく理解して偏見をもたない。
- 認知症の人や家族に対して、温かい目で見守る。
- 近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにできる簡単なことから実践する。
先ほど紹介した男子中学生も、認知症サポーター養成講座を受けた経験がありました。通学路で「何かへん」と思ったことで、「自分なりにできることを実践した」という話でした。
私たちも、必ず年齢を重ねて、高齢者として生活していきます。そして、何らかの助けを必要とする時があると思います。そんな時に、家族や近所の人がどれだけ高齢者について理解があるかが大事になってきます。今回の男子中学生のような判断と行動は、きっと誰かを支える力になり得ると思います。
『菊池市人権未来都市宣言』でも
この宣言文の中でも、「…高齢者等に対する偏見や差別、人権侵害などさまざまな問題が後を絶たない。私たちは、この人類共通の課題を克服していくため、改めて強い決意をもってこの問題に取り組まなければならない」としています。
今こそ私たちは、住み慣れた場所で自分らしく安心してくらすために、小さな一歩を踏み出す時だと思います。
 ◁認知症地域見守り協力店・協力者の家にはしるしとして「大きなオレンジリング」が掲示されています
◁認知症地域見守り協力店・協力者の家にはしるしとして「大きなオレンジリング」が掲示されています
文責:地域人権教育指導員 宮川淳一(みやがわじゅんいち)