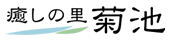錦町「ひみつ基地ミュージアム」に行きました
「山の中の海軍の町にしき ひみつ基地ミュージアム」
戦争中の昭和18年1月に建設が開始された「人吉海軍航空基地」のこと。ここには、終戦を迎える昭和20年8月まで飛行予科練習生の教育や特攻隊の訓練、海軍工廠など様々な役目を持つ部隊が、村一つ分の広大なエリアの中で活躍していた。しかし、終戦後この事実を知る人も減り、徐々に人々の記憶から姿を消していった。戦後75年が経った平成25年に、地元有志の調査・研究によって、当時の姿を鮮明に留める地下施設などの遺構が数多く発見された。ひみつ基地ミュージアムはそれら遺構を展示物と捉え、それらが点在するエリアをフィールドミュージアム(野外博物館)として案内する施設。
(パンフレットより)
菊池市女性団体代表者会と研修してきました。館長による講話では、人吉球磨に航空基地が造られた理由が基地を造る好条件が揃っていたことやパイロットの養成が必要だったことなど教えてくれました。日本各地から約6,000人の海軍飛行予科練習生(14~18歳)が集まり、この地で生活を共にしていたそうです。
館内には、色と形から「赤とんぼ」と呼ばれた布製の翼を持つ九三式中間練習機の実物大模型が展示してありました。当時県内唯一だったコンクリート滑走路は、基地近くに住む女性や子どもたちが勤労奉仕で造ったもので、「滑走路を造るために藪をはらって、トンネルから出る土を運んだ」と語る92歳の女性、海軍施設部設営隊で病院を造った男性、「空襲で お兄ちゃんは跡形もなく、弟は穴が開いて…」と話す女性などを映像で見ました。
地下施設は大きな防空壕の形状で、縦横に繋がる壁一面につるはしの跡が残っていました。
帰りの車中で、戦地に赴き戦後を生き抜いた親戚の話を宮﨑指導員から聞きました。戦争が当人だけではなくそれに繋がる多くの人々の心も傷つける事実を伝えてくれました。戦争は誰一人幸せにはしないと改めて痛感しました。
研修後には、ある人から「花房飛行場で複葉機が練習中に墜落すると、その部品を拾い集めたお礼にお菓子をもらったと親から子ども時代の話を聞いた」という話を思いがけず聞くことができ、当時の子どもたちのたくましい姿を思い浮かべるとともに、戦争を経験した世代が身近にいることも知りました。
ウクライナ対ロシア戦は今年で3年目に入ります。あらゆる命を奪っていく戦争の果てに、未来はあるのでしょうか?
(文責:地域人権教育指導員 末永 知恵美)