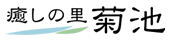「コロナ差別」からの教訓
2020年新聞のスクラップから
先日、ある研修会で「コロナ差別」という言葉を久しぶりに聞き、本棚から当時の地元紙スクラップ帳を出してみました。意外なことに私が最初にスクラップした新型コロナウイルス感染症関連記事は2月28日付でした。前日の「全国の学校に休校を要請」という記事が新聞1面に大きくとりあげられています。国内で最初の患者が報告されたのは1月でしたが、私にとって1月中はまだまだ身近なものではなかったようです。ですから全校休校というニュースもどこか唐突であったと覚えています。
この日、休校の記事とともに2つの記事をスクラップしています。一つはジャーナリスト江川紹子(えがわ しょうこ)さんの視界良好という記事。「新型コロナの情報発信/不安による人権侵害防げ」と題されており、「対応にあたる医療関係者に敬意を払い、デマに惑わされず、できるだけ日常を保ちながらこの難局を乗り切りたい」とまとめられています。もう一つは「トイレットペーパー買い占め騒ぎ/県内」という記事。記事によると、SNSで「新型コロナウイルスの影響で品薄」との情報が拡散したため起きたということです。まさしくデマに惑わされた私たちの姿のニュースです。
水俣病・ハンセン病からの教訓
その後、医療関係者や感染者への差別、県外ナンバーの車への卵投げつけなど様々な事象が起きていきます。5月1日の新聞に「差別と排除/コロナでも」という見出しの記事があります。この日は水俣病公式確認64年目の日でした。その中で当時の熊本学園大学水俣学研究センター長花田昌宣(はなだ まさのり)教授が「根拠のない恐怖や不安が感染者らの攻撃につながる雰囲気は水俣病と重なる」と述べられています。また2022年1月30日には、「ハンセン病療養所の退所者でつくる『ひまわりの会』の中修一(なか しゅういち)会長は『コロナ患者への中傷を見て、教訓は全く生かされていないと感じた』と強調」という記事が残されています。熊本の重要な人権課題である水俣病やハンセン病の教訓が生かされていなかったということです。そのことを忘れてはならないと思います。
「第19回ハンセン病市民学会」
来年5月10日、11日に熊本市で「第19回ハンセン病市民学会」が開催されます。この学会は2005年に、ハンセン病問題を考え、差別や偏見の解消につなげようという目的で作られました。研究者や弁護士、医療関係者だけでなく、広く一般市民にも開かれた会です。ホームページには「交流と検証と提言」を活動方針とし、「差別の現実から学ぶ、回復者の声に学ぶ、そうした姿勢を貫きたい」と書かれています。ぜひ、私たちも市民の立場で参加し、学びたいものです。
(文責:地域人権教育指導員 平井靖彦)