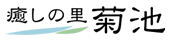同年代のなかまたちのこと(前編)
母のこと
私は1955年(昭和30年)に福岡県大牟田市で生まれました。父は炭鉱労働者でした。私が生まれた頃、合理化をめぐって激しい労働争議が起きていました。死者も出るような騒然とした空気の中、母は心の病気になりました。妄想に支配され、会話も日常生活もできなくなっていきました。小学校高学年の時の担任は、家庭訪問でそんな母を見た後、私への態度が変わりました。近所の大人たちもそうでした。心を病む人への冷たい視線が幼心にもわかりました。大切な存在である母は、いつしか恥ずかしく隠すべき存在になっていました。
友達のこと
1963年(昭和38年)、大規模な炭じん爆発が起こりました。一夜のうちに数百人が亡くなり、逃げ遅れた数百人が一酸化炭素中毒になりました。私の父は幸い難を逃れましたが、友達の中には、中毒の後遺症で働けなくなり、普段は穏やかなのに突然暴力をふるったり暴れだしたりする父親の姿を、なすすべもなくぼう然と見るしかない子もいました。みんなその後、暮らしの困難と世間の冷たさに耐える日々が始まったのでした。
その一方で、爆発で犠牲になった方の中には、与論島や朝鮮半島から来た方、そして被差別部落出身の方がたくさんいました。最前線の危険な場所で働く、そういう人たちに一番に災難が降りかかっていました。彼らの重労働と低賃金の上に父たちの労働も成り立っていたことを、私は大人になって知りました。同じ職場で働くなかまなのに、そこには厳然たる格差がありました。
本当のことを知らねば
その後私は、教員としてある学校に赴任し、校区にある集会所での研修で次の言葉に出会いました。
「親を恨み、このふるさとを恨んで、ここを出ていくような子にだけは、育てるわけにはいかんとです。先生」
ドキリとしました。同じ思いでふるさとを出た自分のことを言われた気がしました。両親を思い、ばい煙にけぶる鉱山町を思いました。「命を与えた親の責任として、つらくても本当のことを子どもに伝えねば、部落差別に負けぬ子にせねば」子を思う親の思いに胸が痛みました。父は、母はどうだったのだろう? 初めて、きちんと向き合わねばと思いました。真実を知らねばと思いました。そして同時代を生き、労苦をともにのりこえた周りのなかまのことにも思いが至りました。
(人権・同和教育シリーズ230へ続く)
文責:地域人権教育指導員 宮崎 篤