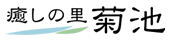概要
児童福祉法に基づくサービスで、原則、菊池市に居住地を有する児童が対象です。
障がい児とは、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある、又は難病等対象者と同程度の障害の疑い等のある18歳未満の児童のことをいいます。
下記リンクをクリックして、菊池圏域地域自立支援協議会(子ども部会)で作成した「障がい児通所サービス事業所一覧」もご覧下さい。
障がい児福祉サービス事業所一覧(R6.8月末現在)(PDF 約4MB)
サービスについて
児童発達支援
・日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
(対象者)
・市町村等が行う乳幼児健診又は医師や心理士、言語聴覚士等により療育の必要性が認められた未就学児。
※サービスの利用にあたっては、必ずしも障害者手帳等が必要ではありません。
放課後等デイサービス
・学校授業終了後や休校日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を学校と連携、協働して行います。
(対象者)
・市町村等が行う乳幼児健診又は医師や心理士、言語聴覚士等により療育の必要性が認められた就学児(学校又は専修学校就学児。但し、幼稚園及び大学を除く) 。
※サービスの利用にあたっては、必ずしも障害者手帳等が必要ではありません。
保育所等訪問支援
・保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、対象児童対して本人以外の児童との集団生活の適応のための専門的な支援を行う。また、保育所等の職員に対し、対象児童に適した専門的な支援方法等の指導等を行います。
(対象者)
・市町村等が行う乳幼児健診又は医師や心理士、言語聴覚士等により療育の必要性が認められた未就学児。
※サービスの利用にあたっては、必ずしも障害者手帳等が必要ではありません。
医療型児童発達支援
・上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童を通所させて、日常生活における適切な習慣を確立するための基本動作の指導や、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。
(対象者)
・上肢及び下肢、又は体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童 。
居宅訪問型児童発達支援
・重度の障害状態等により、外出することが著しく困難で支援が必要と認められる児童の居宅を訪問して発達支援を行います。
(対象者)
・重度の障害状態等にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童 。
障害児相談支援
・障害児福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要です。計画相談支援は、相談支援事業所と契約し、担当となった相談支援専門員が通所先の施設の選定や見学調整、サービス等利用計画を作成、サービス調整をします。障害児相談支援サービスを使っていただくことで、ご本人の状態に応じたサービスを受けることができます。
(対象者)
・障害児福祉サービスを利用するすべての児童。
利用方法
1 利用要件の確認
障害児福祉サービスを利用できるのは、18歳未満かつ、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等対象者、障害の疑い等がある方となります。
申請前に、各種障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援サービス受給者証、特別児童扶養手当証書、医師及び心理士等の診断書又は意見書等をご用意し、申請時に持参してください。
※詳細は下記連絡先へご連絡ください。
2 申請手続き
菊池市役所福祉課又は最寄りの支所(七城、泗水、旭志)の市民生活課にて障害児福祉サービスの申請が必要です。申請書の記入と対象児童の聞き取り調査を行う必要がありますので、時間に余裕をもって来所してください。
※申請手続きは保護者の方のみで行えます(お子さんの同席は不要です)。
※事前に来所のご連絡をいただくと手続きが円滑に行えますのでご協力をお願いします。
3 計画案の提出
相談支援事業所と契約していただくと、担当となった相談支援専門員が通所先の施設の選定や見学調整、サービス調整を行い、サービス等利用計画案を作成し、利用者様の了承を得たうえで市役所に提出されます。
必ずしも相談支援事業所と契約する必要はありませんが、その場合は、ご自身で通所先の施設の選定、契約、計画案の作成、提出を行っていただく必要があります。
4 支給決定
提出された計画案を基に、障害児福祉サービスの支給(利用)決定を行い、支給決定通知書と通所受給者証等を発行します。
※支給決定通知書と通所受給者証等 は申請時の自宅に郵送いたします。
5 利用開始
支給決定通知書と通所受給者証を通所先の事業所に提示し、利用契約を行い、利用開始となります。
利用料
サービス料の自己負担額は原則として、利用料の1割です。ただし、負担額には世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限があります。(非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし)また、利用するサービスによっては、別途、食費や光熱水費等の負担があります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護世帯 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯のうち、所得割28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
申請様式一覧
新規申請
1 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF 約88KB)
更新申請
1 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF 約88KB)
上限管理事業所依頼(新規・変更)届
・利用者負担上限額管理事務依頼(新規・変更)届出書(PDF 約58KB)